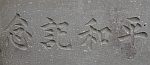
顔を見れば分かるように、石都都古別神社御仮屋の狛犬(昭和14年、大竹俊吉と連名)に似ています。
和平は生前、このように蹲踞したタイプの狛犬を「狛犬」、そうではないもの(立っていたり飛んでいたり)を「唐獅子」と呼んでいたようです。で、「俺の作るのは唐獅子だ」と言っていたそうですから、蹲踞タイプのものは、そういう指定を受けて造ったもので、自由に彫れるときは石都都古別神社のような大胆なものを彫っていたのでしょう。
となると、この赤羽八幡神社の狛犬は「普通の狛犬を造ってくれ」という依頼だったのかもしれません。
気力が欠けていたのか、脚の彫りなど、ずいぶん力がないように見うけられます。
和平の腕を持ってすれば、珠を籠彫りにすることくらいはいくらでも可能だと思いますが、そうした気迫もあまり感じられません。
昭和22年といえば終戦直後で、みんな疲弊していた頃。同行したお袋などは「あの頃はみんな栄養失調だったし、力が出なかったのよ」なんて言っていました。まあ、そういうこともあるのかもしれませんが……。
羽黒神社の馬のような戦時色は消え、顔もどこか穏やかですね。台座に「平和記念」と彫られているのが印象的でした。戦前のダイナミックな作風と比較すると、吐息のような、一種の諦観のようなものさえ感じられます。


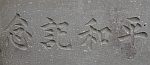 顔を見れば分かるように、石都都古別神社御仮屋の狛犬(昭和14年、大竹俊吉と連名)に似ています。
顔を見れば分かるように、石都都古別神社御仮屋の狛犬(昭和14年、大竹俊吉と連名)に似ています。


 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ